モラハラとは?基本の意味と特徴

モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度で相手の心を傷つけ、心理的に支配・操作する行為です。職場では、業務上の指導の範囲を超えた侮辱や無視、仲間外れなどが典型例です。
パワハラとの違いは、パワハラが「立場や権力の優位」を背景にした行為であるのに対し、モラハラは「心理的支配や人格攻撃」が中心である点です。加害者は自己中心的でプライドが高く、被害者は真面目で周囲に気を遣いやすい傾向があり、こうした心理的特性が背景になりやすいです。
職場におけるモラハラの具体例

- 例1|人格を否定する侮辱
「どうしてこんな簡単なこともできないの?」など、能力や人格を否定する発言。被害者は自信を失い、業務効率が落ちます。 - 例2|会話や連絡を無視
業務連絡や質問を意図的に無視し、孤立感を与える行為。心理的プレッシャーが強く、ストレスが蓄積します。 - 例3|仕事上の嫌がらせ
無理な納期を押し付けたり、ミスを過剰に責めるなど、業務環境を悪化させる行為。モチベーションの低下や疲弊の原因になります。 - 例4|プライベートの過剰詮索・監視
勤務時間外の行動やプライベートの事情を細かく詮索したり、SNSを監視する行為。プライバシー侵害で心理的負担が大きくなります。 - 例5|特定の人を仲間はずれにする
会議や飲み会から排除したり、情報共有を意図的に制限する行為。職場で孤立し、心理的安全が損なわれます。
モラハラをする人(加害者)の特徴

- 自己中心的傾向が強い:自分の意見や感情を優先し、他人の立場を考えない。
- プライドが高い:自分の評価を傷つけられることに敏感で、劣等感を感じると攻撃的になる。
- 他責思考が強い:問題が起きると自分の責任を認めず、常に他人のせいにする。
- 感情の起伏が激しい:怒りや不満を感情的に表現しやすく、被害者を精神的に追い詰めやすい。
モラハラの影響

- 個人への影響:不安や抑うつ、身体的ストレス症状(頭痛・胃痛など)が現れ、業務の効率や創造性が低下します。
- 職場全体への影響:チーム内のコミュニケーションが悪化し、離職率の上昇や生産性低下を招きます。
- 放置するリスク:問題が慢性化すると、職場全体の風土が悪化し、新入社員や有能な人材が定着しにくくなります。
職場におけるモラハラ防止策

- ハラスメント防止方針の明確化と周知
社内規程やガイドラインを作成し、全社員が内容を理解できるよう研修や掲示で周知します。 - 相談窓口の設置
被害者が安心して相談できる窓口を整備し、匿名でも相談可能にすることで早期対応が可能になります。 - 発生時の対応体制の整備
調査・対応・再発防止まで一貫して行える体制を作ることで、迅速かつ公平な対応が可能になります。
モラハラが発生した際に企業がとるべき対応

- 事実関係の調査・ヒアリング
加害者・被害者双方から状況を確認し、客観的な記録を残します。 - 被害者のケア
加害者からの隔離や業務調整を行い、心理的安全を確保します。 - 加害者に対する懲戒処分の検討
注意・指導・処分など、ケースに応じた適切な対応を行います。 - 再発防止策の策定・実施
社内研修やルール改善を行い、同様の被害が再び起きないよう職場環境を整備します。
まとめ|職場のモラハラを理解し、予防・対応するために

- モラハラとは、言葉や態度で相手の心を傷つけ、心理的に支配する行為。パワハラとの違いは心理的支配の有無にある。
- 具体例として、人格を否定する発言、無視、業務上の嫌がらせ、私生活の過剰監視、仲間外れなどがある。
- 加害者の特徴は、自己中心的、プライドが高い、他責思考、感情の起伏が激しいなど。
- 影響は、被害者の精神的ストレスや業務効率の低下、職場全体の生産性低下や離職増加につながる。
- 防止策は、方針の明確化と周知、相談窓口の設置、対応体制の整備。
- 発生時の企業対応は、事実確認・ヒアリング、被害者のケア、加害者への処分、再発防止策の実施が重要。
職場のモラハラは、早期発見・適切対応が重要です。被害者も加害者も孤立せず、組織全体で防止策を整えることが、健全な職場環境の維持につながります。


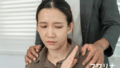
コメント