はじめに

同棲を始めるとき、多くのカップルが悩むのが「住民票をどうするか」「世帯主を誰にするか」という問題です。
これらの手続きを誤ると、手当や行政サービス、会社からの住宅補助、さらには携帯やクレジットカード契約にも影響することがあります。
「よくわからないから、とりあえず住民票を移さない」「どちらが世帯主でも大差ないだろう」と思ってしまいがちですが、実は生活に直結する違いがあるのです。
この記事では、同棲に伴う住民票の移動や世帯主の決め方、それぞれのメリット・デメリット、同棲後に注意すべき点をわかりやすく解説します。
同棲したら住民票は移すべき?
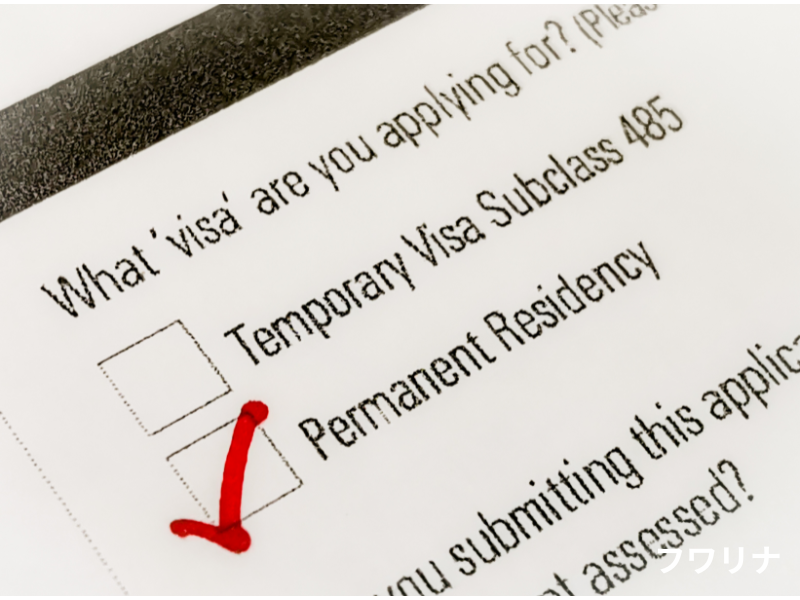
住民基本台帳法により、住んでいる住所に住民票を移すのが原則です。
もし移さないと、法律違反になる可能性があり、手続き上の不便が増えることもあります。
住民票を移さないメリット
- 実家に住民票を残すことで扶養や保険証を維持できる
- 実家の住所で郵便物を受け取れる(身分証の住所と一致するため便利な場合も)
住民票を移さないデメリット
- 役所手続きや選挙権に制限が出る(選挙は旧住所の選挙区でのみ投票可)
- 会社の通勤手当や住宅手当が受けられないことがある
- 賃貸契約や銀行口座、携帯電話契約などで「現住所と身分証の住所が違う」と不便になる
👉 短期間の同棲なら移さなくても良いケースはあるものの、1年以上暮らすなら住民票を移すのが基本的におすすめ です。
同棲での住民票の移し方

同じ市区町村内での引っ越し
役所で「転居届」を提出するだけでOK。比較的シンプルです。
他市区町村への引っ越し
- 転出届:旧住所の役所で提出
- 転入届:新住所の役所で提出(転出証明書が必要)
必要な持ち物
- 印鑑(不要な自治体もあり)
- マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類
- 転出証明書(市外から引っ越す場合のみ)
同棲カップルの世帯主はどう決める?

世帯主をどうするかで、保険・税金・会社の手当などに影響が出ることがあります。大きく3パターンに分けられます。
二人とも世帯主になる(世帯分離)
それぞれを独立した世帯として登録する方法。
→ 保険や扶養関係を分けやすく、経済的に完全に独立しているカップルに向いています。
どちらか一方を世帯主にする
最も一般的な方法。契約や光熱費の名義を一人にまとめられます。
→ 「家を借りた人が世帯主」になるケースが多いです。
片方だけ住民票を移す
もう一方は実家や別住所に住民票を残す方法。
→ 扶養や会社の手当を優先したい場合に選ばれることがありますが、生活実態とずれるので注意が必要です。
世帯主を決めるメリット・デメリット

二人とも世帯主(世帯分離)の場合
- ✅ 保険や扶養関係を独立させやすい
- ✅ 家計を別管理しやすい
- ⚠️ 扶養控除を受けにくいことがある
一方が世帯主の場合
- ✅ 手続きがシンプル
- ✅ 公共料金や契約の名義を一本化できる
- ⚠️ 家計や契約が一人に集中しやすい
世帯分離の注意点
- 扶養控除や健康保険証の扱いに影響することがある
- 税金や社会保険料の計算が変わる可能性あり
同棲生活での注意点(世帯主決定後に大事なこと)

同棲生活をスムーズに送るためには、世帯主を決めた後も以下の点に注意が必要です。
- 家賃・光熱費の分担ルールを明確にする
→ 「家賃は折半、光熱費は収入比率で分ける」など取り決めを最初にしておくとトラブル防止に。 - 家事やプライベート時間を尊重する
→ 生活リズムの違いをすり合わせることが大切。 - 契約名義や保証人を曖昧にしない
→ 契約者をどちらにするか、保証人は誰になるかを明確に。 - 同棲不可物件や会社の家賃補助ルールに注意
→ 契約書で「単身者限定」となっている場合や、会社の家賃補助が「扶養家族との同居のみ対象」ということもあります。
まとめ

- 住民票は原則として移すのが正解
- 世帯主は「二人とも世帯主」か「どちらか一方」かを選ぶ
- メリット・デメリットを理解し、自分たちのライフスタイルに合わせて決めるのが大切
👉 同棲はただの「一緒に住むこと」ではなく、行政上の手続きや税金・社会保険・契約にも関わります。
きちんと準備しておくことで、余計なトラブルを避け、安心して新生活をスタートできます。

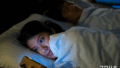

コメント