はじめに
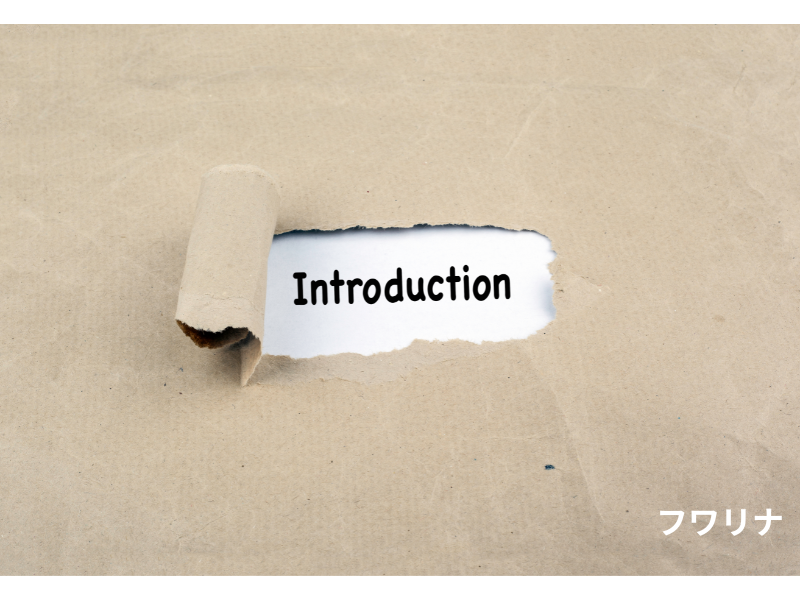
同棲を始めるとき、多くのカップルが直面するのが「世帯主をどうするか」という問題です。
住民票や役所の手続きに関わるため、単純に「名前を書く人」ではなく、税金や保険料にも影響する大事な選択です。
「世帯主は必ず1人?」「同棲なら2人にできる?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、同棲と世帯主の関係をわかりやすく解説します。
そもそも世帯主とは?

世帯主とは、住民票に記載される世帯を代表する人のことです。
- 世帯の中心人物として記録される
- 行政からの通知や税金計算の基準になる
- 住民票や健康保険、税金の申告などで必要になる
必ずしも収入が多い人や家賃の契約者が世帯主になる必要はなく、基本的には自由に選べます。
同棲すると世帯主はどうなる?

同棲する場合、選べるパターンは2つあります。
● 同じ世帯にする場合
- どちらかが世帯主
- もう1人は「同居人」または「未届の配偶者」と住民票に記載
- 一般的に、家賃契約者や収入の多い方を世帯主にするケースが多い
● 別々の世帯にする場合(世帯分離)
- お互いが独立した世帯主になる
- 住民票上は「同じ住所に住む別世帯」という扱い
- 各自が完全に独立した形で税金・保険の計算をされる
● 住民票の続柄の書き方
- 同棲の場合は「同居人」と記載されるのが一般的
- 自治体によっては「未届の配偶者」と書ける場合もある
世帯主を2人にできる?

結論から言うと、1つの世帯に世帯主は1人だけです。
ただし、世帯分離を行えば、同じ住所に住んでいてもそれぞれが世帯主となります。
これが「同棲で世帯主が2人」という表現の正体です。
世帯分離するメリット

世帯を分けることで、次のようなメリットがあります。
- 介護保険料や医療費の自己負担が軽くなる可能性
→ 世帯年収の合算が不要になるため、負担が下がることがある - 低所得者向けの給付金を受けられるケースがある
→ パートナーの収入が高いと受けられない制度も、世帯分離で対象になる可能性がある - 相手の収入に影響されずに制度を利用できる
→ 自分の収入のみで判定されるため、学費補助や医療費助成などの対象になる場合がある
世帯分離するデメリット

一方でデメリットもあります。
- 国民健康保険料が増える可能性
→ 世帯合算での計算ができなくなるため、結果的に高くなるケースがある - 健康保険の扶養から外れることがある
→ 会社員の扶養に入っている場合は、分離によって外れる可能性がある - 介護サービス費の合算ができない
→ 夫婦や家族なら合算できる自己負担上限が、世帯分離するとできなくなる - 役所での手続きが増える
→ 住民票の変更や各種保険の再申請が必要になる
世帯分離の手続き方法
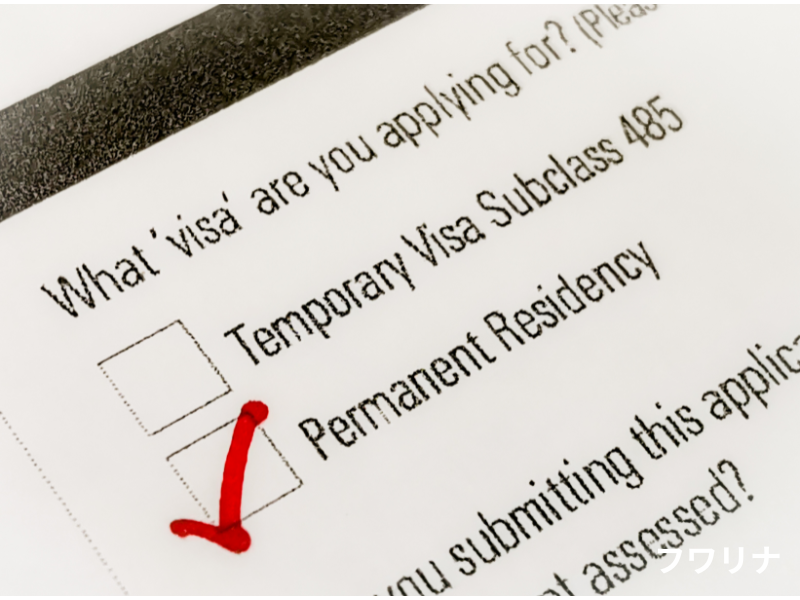
世帯分離は、市区町村の役所で行います。
手続きの流れ
- 役所に「住民異動届」を提出
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)を提示
- 必要に応じて印鑑を持参
- その場で住民票が更新される
注意点
- 世帯分離をしたことで税金や保険料が変わる可能性がある
- 特に国民健康保険や介護保険料は影響が大きいため、事前に役所で試算してもらうのがおすすめ
同棲カップルが世帯主を決める際のポイント

- 将来の結婚や扶養を見据えて決める
→ 結婚予定があるなら、どちらを世帯主にするかを早めに考えておくと安心 - 税金・保険料・給付金の影響を確認する
→ 収入や勤務形態によって有利・不利が変わるため、事前に確認が必要 - よく話し合って決める
→ どちらか一方の都合だけでなく、生活全体を考えて決めることが大切
まとめ

- 世帯主は基本的に1人だけ
- 世帯分離をすれば、同じ住所でもそれぞれ世帯主になれる
- メリット(給付金や負担減)とデメリット(保険料増・扶養から外れる)をよく理解することが重要
- 2人の将来設計を踏まえて、世帯主の決め方を話し合うことがベスト



コメント